Diabetes medicine糖尿病外来
糖尿病専門外来
専門資格を持ったスタッフによる治療
日本糖尿病学会指導医・専門医である医師をはじめとして、糖尿病療養指導士・臨床検査技師・管理栄養士が在籍しチームを組み、それぞれの専門性を発揮することで、最適な医療を提供することを目指しています。
糖尿病診療
サポートチーム
-

-
医師日本糖尿病学会指導医・専門医
問診や検査結果・他のスタッフからの情報をもとに診療方針の提案を行います。
-

-
看護師糖尿病療養指導士
個別インタビューにより、医師の診察よりも生活に踏み込んだ情報を聞き取り、療養に関するアドバイスを行い、医師に助言します。
-

-
臨床検査技師
糖尿病の定期検査をはじめ、合併症の早期発見のために必要な検査を適切なタイミングで実施できるよう計画し、検査を行います。
-

-
管理栄養士
画一的なものではなく、一人ひとりの状況に合わせて、継続的に実行できる食事内容を提案します。
充実した検査体制
当院は、糖尿病やその合併症に関する検査機器の設置や臨床検査技師を配置することで、充実した検査体制を有しています。
| 血液・尿検査 | 血糖・脂質・肝機能・腎機能等の現在の状態を調べます。 |
|---|---|
| 超音波(エコー)検査 | 心臓エコー心機能(弁膜症)を調べます。頚動脈エコー動脈硬化の進行度合いを調べます。 |
| 心電図 | 不整脈・狭心症の症状がないかを調べます。 |
| PMV・ABI | 下肢動脈の狭窄の有無や血管の硬さ(血管年齢)を調べます。 |
| DPN | 糖尿病性神経障害の有無を検査します。 |
| 眼底検査 | 糖尿病性変化・動脈硬化性変化・高血圧性変化の有無を調べます。 |
| 胸部レントゲン | 心臓が肥大していないか、レントゲン画像で確認します。 |

- 採血せずに普段の生活中の血糖値がわかる検査
-
上腕に貼ったセンサーが、血糖値を常時測定します。
スマートフォンをかざすと専用アプリで手軽に血糖の動きを見ることができます。
ご自身の1日の行動と血糖の変化を照らし合わせることで、より効果的な治療が可能となります。
一人ひとりの症状や環境に合わせたオーダーメイド治療
当院の糖尿病診療は、「患者さん中心のオーダーメイド医療」を提供することをモットーとしています。 患者さんとの信頼関係を築き、一人ひとりの生活習慣や環境を知ることで、その方に最適な医療を提供したいと思っています。
診療実績
1型・2型糖尿病患者数(年度別)
糖尿病の症状
糖尿病とは?
血液中の糖分(ブドウ糖)の濃度=血糖値が高くなる病気です。
正常な人の血糖値は、食事前の空腹時で70~110mg/dlぐらいで、食事を摂ることで糖分が吸収されると血糖値も上がりますが、140mg/dlぐらいです。
通常は膵臓から分泌されるインスリンの作用により、ブドウ糖を分解し筋肉や脂肪に取り込むことで適正な血糖値を保っていますが、インスリンが何らかの原因で作用しない状態になることで糖尿病を引き起こします。
血糖値が高いとどうなるの?
極端に高いと、命にも関わる危険な状態ですので、すぐに治療を受ける必要があります。
通常はすぐに症状が出ませんが、時間の経過とともに様々な病気を引き起こすため、放っておくと非常に怖い病気です。
※HbA1cとは?
健康診断等で、「HbA1c」という検査項目を目にしたことはありませんか?
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)とは、採血した日より1~2ヶ月前ぐらいまでの血糖値の状況を示すものです。この値が高い場合は、随時血糖(採血した時点での状態)が低くても、1~2ヶ月の間は血糖値が高かったということになります。糖尿病の治療において重要な検査項目です。
予防や治療の方法は?
血糖値を適正な値に保ち糖尿病にならないためには、日頃の生活習慣が重要です。血糖値が高くなりにくい食生活や日頃の運動によりインスリンの働きをよくすることも大事です。糖尿病になった後も同様で、生活習慣の改善に加え、患者さんの状態に合わせた適切な治療方法を組み合わせることで血糖値をコントロールします。
糖尿病にも種類があるの?
糖尿病は4つの種類に分類されますが、主なものとして、1型糖尿病と2型糖尿病が挙げられます。
- 1型糖尿病
- 遺伝的な要因やウイルス感染によって、膵臓がインスリンを作り出せなくなることで血糖値が高くなります。
- 2型糖尿病
- 遺伝的な要因もありますが、多くは生活習慣などによって、膵臓からのインスリンによる血糖コントロールができない状態になります。
高血糖の状態が続くと、次のような症状が現れることがあります。
これらに思い当たる方は、ご遠慮なくご相談ください。
- のどが渇く
- 水分摂取量が増える
- 手足がしびれる
- 尿量が増える
- 体重減少
- 倦怠感
糖尿病による合併症について
糖尿病の最も怖いところが、深刻な合併症です。糖尿病では、主に血管や神経がダメージを受けることで様々な器官に合併症が発生します。
- 網膜症
- 眼の網膜の血管がダメージを受けることで発症し、進行すると失明します。
- 腎症
- 腎臓の細い血管のダメージにより、老廃物を体外へ排出する機能が失われ、進行すると透析治療が必要となります。
- 神経障害
- 末梢神経がダメージを受けることで、身体中の様々な場所に症状が現れます。痛みやしびれ、感覚が麻痺するなどの皮膚異常が現れます。
- 脳卒中、心筋梗塞
-
糖尿病は動脈硬化を引き起こします。これにより脳卒中や心筋梗塞が起こりやすい状態になります。
また、糖尿病に加えて肥満や高血圧、脂質異常が加わるとさらにリスクが高まります。
治療方針と流れ
糖尿病の治療には大きく分けて、以下の3つの療法があり、一人ひとりに最適な方法を組み合わせて計画を作成します。
-

-
食事療法
日々の食生活改善は、糖尿病治療の基本です。
カロリーや糖質を制限するだけでなく、栄養バランスの取れた食事を摂ることが重要です。
医師による指導だけでなく、管理栄養士による栄養指導も行っています。
-

-
運動療法
運動は摂取したブドウ糖や脂肪を消費するだけでなく、インスリンの働きを高める効果も期待できます。
ただし、過度な運動や不適切なやり方で行うと、かえって糖尿病を悪化させたり、他の疾患を発症させることもありますので、医師の指示に従って適切に行うことが重要です。
-
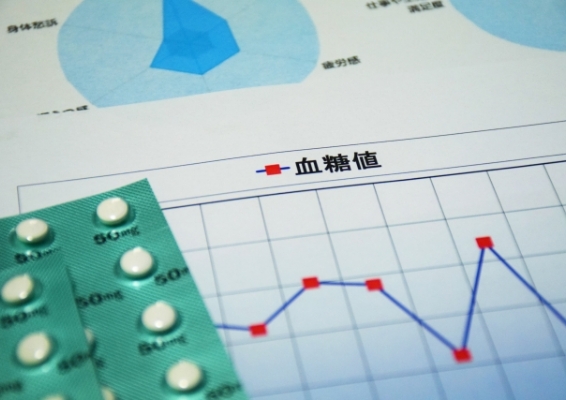
-
薬物療法
健康関連イベント
地域住民の皆様の健康増進や病気の予防などに貢献するために、セミナーなどのイベントを開催しています。
また、今後は糖尿病教室等を企画し、療養のサポートを行いたいと考えています。


診療カレンダー
午前 9:00~13:00/午後 14:00~18:00
※土曜日午後・日曜日・祝日は休診です。

